
このページでは予防技術検定(防火査察)の過去問や類似問題、予想問題を公開しています。
問題にひたすらトライアル&エラーを繰り返すことで短時間で効率よく学習できるページです。間違えた問題は法令や解説ページで復習をすることでさらに効果的ですよ。
第4回目は防炎と防火対象物の定期点検制度、行政手続法についてです!
防火査察区分や共通科目で頻出分野である防炎対象物品や防火対象物の定期点検制度、行政手続法に関連する問題を厳選しています。特に違反処理標準マニュアルに関連する問題は必ず出題されると言っても過言ではなく、警告や命令、不利益処分での意見陳述のための機会の付与については正しく理解する必要があります。しっかりと用語を整理した中で問題に取り組み、間違えた問題や理解できなかった文章は復習を心がけましょう!
防火査察の問題にチャレンジ! 防炎関連
防炎対象物品を使用しなければならない用途について(問題数2)
消防法第8条の3に定められる防炎性能を有する防炎対象物品を使用しなければならない防火対象物の用途について誤っているものを1つ選べ。
- 消防法施行令別表第1(3)項ロ
- 消防法施行令別表第1(6)項ハ
- 消防法施行令別表第1(12)項ロ
- 消防法施行令別表第1(13)項イ
消防法第8条の3に定められる防炎性能を有する防炎対象物品を使用しなければならない防火対象物の用途について誤っているものを1つ選べ。
- 高さ31メートルの共同住宅
- 地下街
- 16項イにおける6項イ(4)の部分
- 16項イにおける12項ロの部分
防炎物品に求められる性能について(問題数2)
消防法第8条の3に定められる防炎性能を有する防炎対象物品を使用しなければならない防火対象物についての記述について、誤っているものを1つ選べ。
- 工事中の建築物に使用される工事用シートは防炎性能を有する必要がある。
- カーテンに求められる防炎物品としての性能は炎を接した場合に溶融する性状を有していれば、物品の残炎時間、残じん時間、炭化面積、炭化長及び接炎回数について一定の基準を満たすことが要求されている。
- じゅうたん等に求められる防炎物品としての性能に物品の残じん時間、炭化面積及び接炎回数について一定の基準を満たすことは求められていない。
- 炎を接した場合に溶融する性状を有しない展示用の合板に求められる防炎物品としての性能は、物品の残炎時間及び物品の炭化面積についての2種類だけである。
消防法施行令第4条の3に定められる防炎性能についての記述について、誤っているものを1つ選べ。
- 残炎時間とは着炎後バーナーを取り去ってから炎を上げて燃える状態が止むまでの時間経過をいう。
- 残じん時間とは着炎後バーナーを取り去ってから炎を上げずに燃える状態が止むまでの時間経過をいう。
- 炭化面積とは着炎後燃える状態が止むまでの時間内において炭化する面積をいう。
- 接炎回数とは物品が燃焼を始めるまでに必要な炎を接する階数をいう。
防火査察の問題にチャレンジ! 防火対象物定期点検と特例編
防火対象物の定期点検が必要な防火対象物について(問題数2)
消防法第8条の2の2に定められる防火対象物の点検及び報告について、以下の防火対象物のうち制度の対象となるものとして誤っているものを1つ選べ。
- 収容人員50人である特定一階段等防火対象物である飲食店
- 収容人員が20人である特定一階段等防火対象物である老人短期入所施設
- 収容人員が400人である物品販売店舗
- 収容人員が600人である美術館
消防法第8条の2の2に定められる防火対象物の点検及び報告についての記述について、誤っているものを1つ以上選べ。
- 大規模な建築物であっても防火管理者の選任義務を有していなければ消防法第8条の2の2に定められる防火対象物の点検及び報告制度の対象にはならない。
- 市町村の消防職員で火災予防に関する業務について1年以上の実務の経験を有する者は登録講習機関の行う課程を修了しなくても防火対象物の点検を実施することができる。
- 収容人員が100人の(6)項ロは防火対象物定期点検報告制度の対象となる。
- 3階部分が(3)項ロの用途である放火対象物において、防火管理制度の適用を受け、屋内の直通階段が1つしかないものは防火対象物定期点検報告制度の対象となる。
防火対象物定期点検の点検内容について(問題数1)
消防法第8条の2の2に定められる防火対象物定期点検の点検基準についての記述のうち、誤っているものを1つ選べ。
- 防火管理に係る消防計画の届出がされていること。
- 自衛消防組織の適用を受ける大規模な防火対象物にあっては自衛消防組織を設置する届出がされていること。
- 消防法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について適切に管理されていること。
- 消防法第17条の3の3に基づく点検報告が定期に実施されていること。
防火対象物定期点検特例について(問題数2)
消防法第8条の2の3に定められる防火対象物の点検及び報告の特例を認定するための要件について、誤っているものを1つ選べ。
- 申請者が当該防火対象物の管理を開始した時から3年が経過していること。
- 過去3年以内において、防火対象物定期点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことが無いこと。
- 消防法第17条の3の3の規定を遵守していること。
- 防災管理制度の適用を受ける防災対象物にあっては防災管理に基づく消防計画に定められる日常点検や定期点検が実施され、適切に記録が保管されていること。
消防法第8条の2の3に定められる防火対象物の点検及び報告の特例を認定した場合に掲げられる表示について、記載される事項として正しいものを1つ以上選べ。
- 特例の認定を受けた日
- 特例認定の効力が失われる日
- 権原を有するものの氏名
- 認定を行った消防長又は消防署長の消防本部又は消防署の名称
防火査察の問題にチャレンジ! 行政手続法関連
行政手続法概論(問題数2)
行政手続法に関する記述について誤っているものを1つ選べ。
- 行政手続法の目的は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することである。
- 処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する行為をいう。
- 申請とは法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
- 行政指導とは行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
不利益処分についての記述について、適切でないものを1つ選べ。
- 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分は不利益処分にあたらない。
- 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分は不利益処分にあたらない。
- 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるものは 不利益処分にあたらない 。
- 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分であっても直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する行為であれば不利益処分に該当する。
警告と命令(問題数1)
警告や命令に関する記述について適当でないものを1つ選べ。
- 警告とは、違反事実又は火災危険等が認められる事実について、防火対象物の関係者に対し、当該違反の是正又は火災危険等の排除を促し、これに従わない場合、命令、告発等の法的措置をもって対処することの意思表示である。
- 警告は命令の前段的措置として行うのが原則で、性質上行政指導にあたるが、一定の強制力を有する。
- 命令は、行政庁としての市町村長、消防長又は消防署長などの命令権者が消防法令の命令規定に基づき、公権力の行使として、特定の者に対し、具体的な火災危険の排除や消防法令違反の是正について、義務を課す意思表示であり、通常、罰則の裏付けによってその履行を強制している
- 命令は特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限するため不利益処分である。
意見陳述の機会の付与(問題数2)
不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、意見陳述のための手続を執る必要があるが、次の文章のうち、適切でないものを1つ選べ。
- 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときに選択する意見陳述の機会は「聴聞」である。
- 名宛人の資格又は地位を剥奪する不利益処分をしようとするときに選択する意見陳述の機会は「弁明」である。
- 消防計画未作成を理由として消防法第8条第4項に基づく防火管理業務適正執行命令を発動する場合、「弁明」の機会を与えることが必要である。
- 建物に1つしかない屋内階段内に多量の可燃物が存置されており、これらを消防法第5条の3第1項に基づく除去命令で移動させる場合、公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、意見陳述のための手続を執ることができないと判断し、聴聞や弁面の機会を与えなかった。
消防法に基づく命令について、次の不利益処分を実施しようとするときに聴聞が必要なものを1つ選択せよ。
- 防火管理者選任命令
- 消防用設備等設置命令
- 消防計画作成命令
- 防火対象物定期点検特例の取り消し
おわりに
今回は防炎物品、防火対象物の定期点検制度及び行政手続法についての内容でした。間違えた問題や正解するまでに時間を要した問題は必ず法令文等で深く学習するようにしましょう。聴聞や弁明の選択は法文で考えるより表を視覚的に暗記してしまいましょう!
| 命令 | 根拠法令 | 意見陳述の機会の付与 |
|---|---|---|
| 防火対象物に対する措置命令 | 法第5条 | 弁明 |
| 防火対象物に対する使用停止命令 | 法第5条の2 | 弁明 |
| 防火対象物における措置命令 | 法第5条の3 | なし |
| 防火管理者選任命令 | 法第8条第3項 | なし |
| 防火管理業務適正執行命令 | 法第8条第4項 | 弁明 |
| 防火対象物定期点検特例の取り消し | 法第8条の2の3第6項 | 聴聞 |
| 消防用設備等の設置維持命令 | 法第17条の4 | なし |
| 消防設備士免状の返納命令 | 法第17条の7 | 聴聞 |


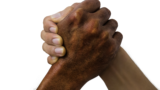



コメント