
このページでは予防技術検定(消防設備)の過去問や類似問題、予想問題を公開しています。
問題にひたすらトライアル&エラーを繰り返すことで短時間で効率よく学習できるページです。間違えた問題は法令や解説ページで復習をすることでさらに効果的ですよ。
第4回目は消防同意、消防設備の設置維持義務、飲食店の消防法改正、特定小規模施設についてです!
予防技術検定の消防設備や共通科目では消防同意や消防設備の設置維持義務についての問題が必ずと言っても過言ではない頻度で出題されます。これらの王道問題を確実に得点するためには問題のトライアルアンドエラーの繰り返しが非常に重要です。このページでは消防同意、消防設備の設置維持義務、飲食店法改正、特定小規模施設についてのチャレンジ問題に取り組み、自己学習が可能です。
消防設備、共通科目の問題にチャレンジ! 消防同意編
消防同意の要否(問題数2)
防火地域及び準防火地域以外の地域における消防同意の説明について、誤っているものを1つ選べ。
- 一般住宅を新築する場合、消防同意が必要である。
- 長屋を新築する場合、消防同意が必要である。
- 共同住宅を新築する場合、消防同意が必要である。
- 延べ面積20㎡の駐輪場を新築する場合、消防同意が必要である。
消防法第7条に定められる消防同意の記述について、誤っているものを1つ選べ。なお、建築物の高さ及び軒高については考慮しないものとする。
- 延べ面積300㎡、2/0、木造の事務所は3日以内に同意又は同意できない旨を通知しなければならない。
- 延べ面積150㎡、平屋建て、鉄骨造の飲食店は3日以内に同意又は同意できない旨を通知しなければならない。
- 延べ面積200㎡、平屋建て、鉄骨造のコンビニは3日以内に同意又は同意できない旨を通知しなければならない。
- 延べ面積300㎡、平屋建て、鉄骨造の無床診療所は7日以内に同意又は同意できない旨を通知しなければならない。
消防同意の日数(問題数1)
消防法第7条に定められる消防同意の日数について、次の表の(ア)から(ウ)にあてはまるものを選べ。
| 建基法第6条第1項 | 構造 | 階数 | 延べ面積 | 消防同意の日数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2号 | 木造 | (ア)階以上 | (ウ)㎡を超える | 7日以内 |
| 第3号 | 木造以外 | (イ)階以上 | 200㎡を超える | 7日以内 |
- (ア)2、(イ)1、(ウ)300
- (ア)3、(イ)1、(ウ)500
- (ア)3、(イ)2、(ウ)300
- (ア)3、(イ)2、(ウ)500
消防設備、共通科目の問題にチャレンジ! 消防設備の設置維持と附加条例
消防法第17条第1項関連(問題数2)
消防法第17条第1項にて防火対象物の関係者は消防用設備等について設置し維持することが義務付けられているが、その対象として誤っているものを1つ選べ。
- 地下街
- 重要文化財として指定された個人の住居
- アーケード
- 150㎏以上の高圧ガス(可燃性ガス及び酸素に限る)を運送する自動車
消防法第17条第1項にて防火対象物の関係者は消防用設備等について設置し維持することが義務付けられているが、これらの義務を負う関係者について適当でないものを1つ選べ。
- 防火対象物又は消防対象物の所有者は消防用設備等の設置及び維持の義務を負う対象になり得る。
- 防火対象物又は消防対象物の管理者は消防用設備等の設置及び維持の義務を負う対象になり得る。
- 防火対象物又は消防対象物の占有者は法的な契約書等に基づいて防火対象物又は消防対象物を占有する場合に限り、消防用設備等の設置及び維持の義務を負う対象になり得る。
- 分譲マンションに設置される自動火災報知設備は法定共有部分に該当し、区分所有者全員が所有者として消防用設備等の設置及び維持の義務を負う対象になり得る。
消防法第17条第2項関連(問題数1)
消防法第17条第2項の附加条例についての記述について適当でないものを1つ選べ。
- 附加条例を定める事ができるのは「その地方の気候又は風土の特殊性」により、法令のみによっては「防火の目的を十分に達し難いと認めるとき」に限られるため、全国的に共通する一般的な理由により附加条例を設ける事は出来ない。
- 「その地方の気候又は風土の特殊性」により、防火の目的を十分に達成できていると認める場合においては、施行令又は施行規則に基づく基準を消防法第17条第2項に基づく附加条例により一部緩和することは可能である。
- 附加条例によって施行令別表第一に掲げられていない防火対象物に何らかの消防用設備等の設置を義務付ける事や、同表に掲げられている防火対象物であっても施行令第7条に定められる設備以外の設備の設置を義務付けることは原則できない。
- 附加条例は当該市町村の区域内においては、本条第1項による法令又はこれに基づく命令の特例としての効力を有するため、当該規定は設置・維持の技術上の基準の1つとなる。
消防設備の問題にチャレンジ! 小規模な飲食店関連
飲食店における消防用設備等の設置基準について(問題数2)
消防法施行令第10条(消火器に関する基準)の記述について、誤っているものを1つ選べ。
- 飲食店における消火器について、防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられた火を使用する設備が設けられた防火対象物は延べ面積が150㎡以上で設置義務が生じる。
- 飲食店において無窓階で床面積が50㎡以上の階には消火器の設置義務が生じるが、換気について有効な開口部の面積が床面積の1/30以下で25㎡以下の居室には二酸化炭素を放出する消火器は設置することができない。
- 防火上有効な措置として総務省令で定める措置に、調理油過熱防止装置は含まれる。
- 防火上有効な措置として総務省令で定める措置に、立ち消え防止装置は含まれる。
小規模な飲食店に係る規制に関する記述について、適当でないものを1つ選べ。
- 地上2階建て、木造、延べ150㎡の一般住宅を飲食店に用途変更する際、建築確認申請や消防同意は不要である。
- 平屋建て、延べ90㎡の飲食店について、無窓階である場合、収容人員が20人以上であれば非常警報設備の設置が必要である。
- 地上2階建て、延べ200㎡の飲食店について、2階の収容人員が11人である場合、避難器具の設置が必要である。
- 地上2階建て、延べ200㎡の飲食店について、2階に避難器具の設置義務が生じる場合、適応するものとされる避難器具に避難ロープは含まれる。
小規模特定飲食店等について(問題数1)
小規模特定飲食店等の記述について、誤っているものを1つ選べ。
- 防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられた火を使用する設備を除く火を使用する設備を設けた飲食店で延べ面積が150㎡未満のものは「小規模特定飲食店等」という。
- 消火器の設置義務を有する防火対象物において、多量の火気を使用する場所があるときは、能力単位の数値の合計数が当該場所の床面積を25㎡で除して得た数以上を附加設置する必要があるが、小規模特定飲食店等はこの基準から全て除かれる。
- 「小規模飲食店等」であっても住宅用消火器を設置することはできない。
- 地上2階建て延べ面積80㎡(1階及び2階はそれぞれ40㎡)の小規模特定飲食店等で少量危険物又は指定可燃物の貯蔵取扱が無いもので、防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられた火を使用する設備を除く火を使用する設備を設けた階が1階のみである場合は2階に消火器の設置義務は生じない。
消防設備の問題にチャレンジ! 特定小規模施設編
特定小規模施設について(問題数1)
次の防火対象物について、特定小規模施設の定義に該当しないものを1つ以上選べ。ただし、全ての選択肢は令別表第一(16)項イに掲げる防火対象物であり、特定1階段等防火対象物ではないものとする。
- 延べ面積200㎡で令別表第一(5)項イに掲げる用途の面積が150㎡、(15)項に掲げる用途の面積が50㎡のもの。
- 延べ面積450㎡で令別表第一(5)項イに掲げる用途の面積が250㎡、(5)項ロに掲げる用途の面積が200㎡のもの。
- 延べ面積300㎡で令別表第一(6)項ロ(1)に掲げる用途の面積が100㎡、(15)項に掲げる用途の面積が200㎡のもの。
- 延べ面積350㎡で令別表第一(2)項ニに掲げる用途の面積が20㎡、(3)項ロに掲げる用途の面積が20㎡、(15)項に掲げる用途の面積が310㎡のもの。
特小自火報について(問題数2)
特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準の記述について、誤っているものを1つ以上選べ。
- 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置工事について、警戒区域が1であり、中継器の設置が不要な規模であれば消防設備士工事の独占業務には該当しない。
- 床面積が4㎡未満の収納室には感知器が不要である。
- 床面積が30㎡以下の居室であれば、感知器を壁に設置することができる。
- 倉庫、機械室その他これらに類する室の壁に感知器を設置することはできない。
次の防火対象物について特定小規模施設用自動火災報知設備が設置できない用途を1つ選べ。
- 6項イ(1)
- 5項イ
- 3項ロ
- 2項ニ
おわりに
今回は共通科目でも頻出である、消防同意や消防法第17条関連についての出題と、近年の法改正内容である小規模な飲食店や特定小規模施設についての内容でした。間違えた問題や正解するまでに時間を要した問題は必ず法令文等で深く学習するようにしましょう。 試験日まで僅かですので、自身の知識を整理するとともにメンタルや体調管理にも気を配って下さいね。
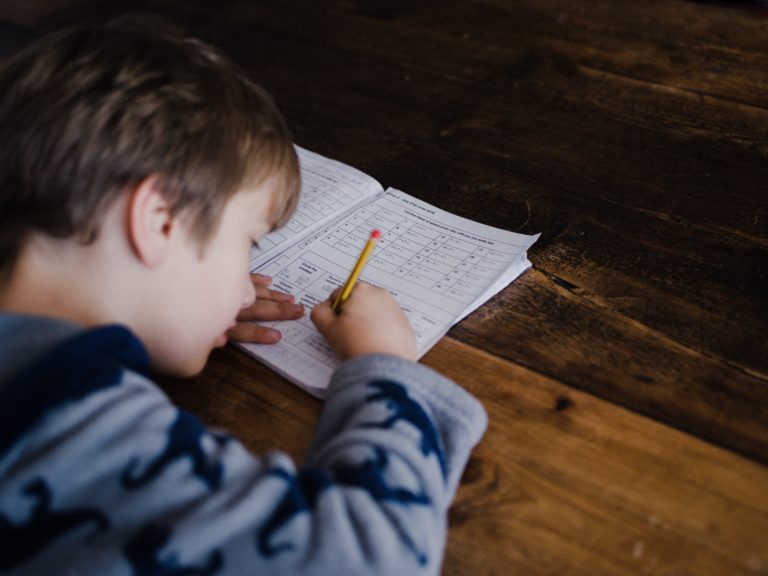






コメント